
経験を重ねても、
常に新鮮な気持ちを忘れずに。
2014年入社。北海道出身。学校卒業後、幼稚園6年間勤務。
その後、引っ越しや、結婚・出産をし、しばらくは子育てに専念。社会福祉法人の園での主任職等を経た後、友人からの勧めもあり2014年グローバルキッズに入社。
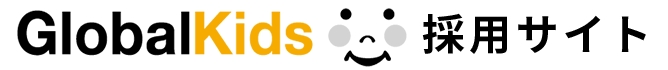
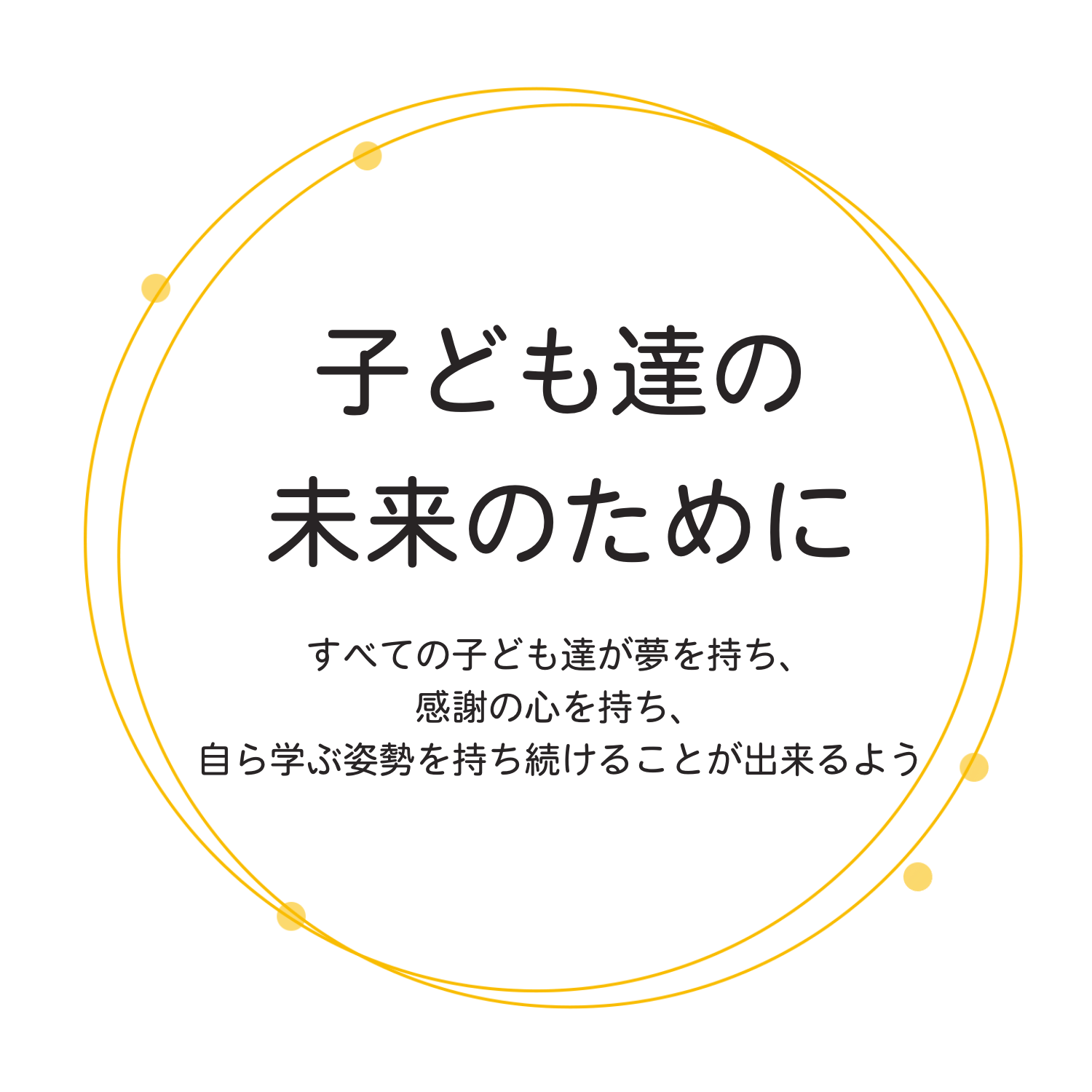

VIDEO
EVENT

【保育士職対象/オンライン】 ★2025年卒の方おすすめ グローバルキッズは 「子ども中心の保育」 ・目の前の子ども達 ・そこにある環境 ・先生たちの経験 150以上の施設を運営する中で、 全て同じではないからこそ、 各施設で主体的な保育を …

【保育士職対象/オンライン】 ★2025年卒の方おすすめ グローバルキッズは 「子ども中心の保育」 ・目の前の子ども達 ・そこにある環境 ・先生たちの経験 150以上の施設を運営する中で、 全て同じではないからこそ、 各施設で主体的な保育を …

【保育士職対象/現地&WEB開催】 ★現地、WEB参加をお選びいただけます グローバルキッズ保育園の 保育室内を大公開👀✨ 実際に保育している様子を 見学していただきながら、 グローバルキッズの 大切にしたい思 …

【保育士職対象/現地&WEB開催】 ★現地、WEB参加をお選びいただけます グローバルキッズ保育園の 保育室内を大公開👀✨ 実際に保育している様子を 見学していただきながら、 グローバルキッズの 大切にしたい思 …

【保育士職対象/現地&WEB開催】 ★現地、WEB参加をお選びいただけます グローバルキッズ保育園の 保育室内を大公開👀✨ 実際に保育している様子を 見学していただきながら、 グローバルキッズの 大切にしたい思 …

【保育士職対象/オンライン】 ★2025年卒の方おすすめ グローバルキッズは 「子ども中心の保育」 ・目の前の子ども達 ・そこにある環境 ・先生たちの経験 150以上の施設を運営する中で、 全て同じではないからこそ、 各施設で主体的な保育を …
OUR MEMBER

2014年入社。北海道出身。学校卒業後、幼稚園6年間勤務。
その後、引っ越しや、結婚・出産をし、しばらくは子育てに専念。社会福祉法人の園での主任職等を経た後、友人からの勧めもあり2014年グローバルキッズに入社。

2014年入社。子ども時代は、お家が大好き。お母さんと離れたくなくて、幼稚園が嫌いな子どもだった。とにかく子どもが好きで、子どもと関わる仕事を志す。新卒でグローバルキッズに入社。

2014年入社。専門学校卒業後、社会福祉法人の園で5年勤務する。その後以前から興味のあった幼稚園での勤務を経て、グローバルキッズへ入社。横浜市内の園に配属。2016年度から新規開園の園に異動。ドライブが好きで、休日にはよく車に乗って出かけている。

2013年入社。子どもの頃から食べることが大好きで、子どもの頃に楽しい食体験をさせてあげたいという想いから、保育園への就職を希望。大学卒業後、グローバルキッズに入社。

2013年入社。昔から子どもが好きで、幼稚園教諭、保育士、小児科の看護師になりたいと思っていた。学校卒業後は幼稚園教諭として勤務。幼稚園で病気を持つ子ども達と関わったことをきっかけに、看護の道を志す。

2012年入社。昔から子どもが好きで「何か資格がある職業に就きたい」ということもあり、子どもに関わる仕事を志す。短大卒業後は幼稚園で5年半勤務。結婚、出産を経て仕事に復帰。派遣社員を経験後、グローバルキッズに入社。

2014年入社。埼玉県出身。高校時代は甲子園を目指す野球少年だった。専門学校卒業後、川口市内の公立保育所で非常勤として勤務する。その後、静岡市の公務員試験に合格し、10年間公立の保育所で勤める。
ENNVIROMENT

休暇制度や社宅制度・子育て職場環境の整備、GKアプリや、声を届けるリンカーン会議、婦人科検診は会社負担など、より働きやすくなるための環境づくりについてご紹介します。

「学び続ける人を育てる」をモットーに、保育基礎研修や保育者向け実践研修など、次の日から活かせるスキルや知識を学べる様々な研修を行なっています。

海外の保育施設をめぐる、充実の海外研修プログラム。各国の様々な保育制度・保育技術についてを深めるためにフィンランド・ハンガリーなど世界各区にて海外視察旅行を実施しています。

グローバルキッズは「子ども達の未来のために」、子どもを中心にした保育の実践がもっとも大切であるとこころえています。私たちの信念をご紹介します。